「就業規則に副業禁止って書いてないんだけど、これってやってもいいの?」——そんな素朴な疑問、あなたも感じたことありませんか?特に副収入を得たい今の時代、副業を始める人が増える一方で、就業規則に明記がないと「グレーゾーン」な感じがして不安にもなりますよね。
この記事では、就業規則に副業禁止が書いていない場合の実際のリスクや注意点、やっていい副業・まずい副業の違いなどをわかりやすく解説します。会社とのトラブルを避けつつ、自分らしい働き方を実現するためのヒントをお届けしますね。
就業規則に副業禁止と書いてないのに「副業ダメ」って言われるのはなぜ?

就業規則を隅々まで読んでも「副業禁止」の一文が見つからない。それなのに「副業は認めてません」なんて言われると、ちょっと納得いかないですよね。でも実は、「書いてない=自由」ではないのが現実なんです。
なぜなら、副業が直接書かれていなくても、就業中の誠実義務や職務専念義務、会社の信用保持義務などに引っかかる可能性があるからです。つまり、副業によって会社に不利益が出ると判断されれば、懲戒の対象になり得るということ。
また、人事や上司が「就業規則に書いてないからセーフ」と捉えていない場合、職場での立場が悪くなることもあるんですよね。実際、そうしたことで同僚から「告げ口」されたり、居心地が悪くなるケースも聞かれます。
就業規則に副業禁止の記載がない場合こそ、逆に注意が必要とも言えるんです。
- 職務専念義務や信用保持義務に抵触する場合がある
- 就業規則にないことでも社内慣習でNGとされることがある
- 副業が原因で本業に支障が出れば懲戒対象にもなり得る
要約:副業禁止の明記がなくても、別の規定でアウトになる可能性はあるので慎重な判断が必要。
なぜ「明記されていない副業禁止」でも問題になるの?
副業について明記されていない場合でも、労働者には「信義則に基づいた行動」が求められています。例えば、深夜に副業で疲れて本業で集中力を欠いたり、競業にあたる業種で働いて情報漏洩が疑われたりすれば、結果的に会社の不利益になりますよね。
こうした場合は、就業規則に「副業禁止」とは書かれていなくても、信用失墜行為や服務違反として処分される可能性があるのです。だからこそ、「書いてないからOK」という発想には少しブレーキをかけて、客観的にリスクを判断する目が大切なんです。
副業がバレたらどうなる?就業規則に書いてない場合のリアルな処分例

「うちは副業禁止なんて書いてないから大丈夫」そう思って始めた副業が、ひょんなきっかけでバレてしまった…なんてことも実際にあるんです。では、そのときどうなるのでしょう?
処分内容は会社によって異なりますが、注意、始末書、減給、出勤停止、ひどい場合には懲戒解雇まで幅があります。ポイントは、「会社に不利益を与えた」と見なされるかどうか。そこが判断基準になっています。
たとえば、以下のようなケースでは処分リスクが高まる傾向があります。
- 同業他社や競合企業で働いていた
- 本業に明らかに悪影響が出ていた(遅刻・ミス・疲労など)
- 収入申告のズレで住民税額が変わり経理に発覚
要約:副業が発覚しても処分されないケースもありますが、上記に当てはまると一気に厳しい対応になる可能性が高くなります。
「処分される副業」と「見逃される副業」の違いとは?
副業がバレても見逃される人がいる一方で、厳しく処分される人もいます。その違いは主に「副業の影響度」と「会社の対応方針」によるんです。たとえば、趣味の延長でたまにフリマアプリに出品する程度なら、黙認されることもあります。でも、深夜の飲食店で毎晩働いていて昼間の本業に影響していると判断された場合、たとえ就業規則に副業禁止と書いてなくてもアウト。大切なのは「会社に迷惑をかけていないか」という観点です。
副業がバレるきっかけはどこにある?意外な発覚ルートに注意
「こっそりやってるしバレないでしょ」と油断している方、意外と多いんですが、思わぬところから副業が発覚することもあるんです。特に注意したいのが、以下のようなケース。
- 住民税の額が副業分で増えて経理担当に気づかれる
- 同僚や友人からの“密告”で発覚
- SNSや副業先の情報が社内で見つかってしまう
要約:意図しないルートから副業が知られるリスクがあるため、バレたら困る副業は慎重に選び、情報管理も徹底する必要があります。
住民税やSNSからバレる副業、本当に多いんです
特に多いのが、住民税の「特別徴収」ルート。副業の所得を確定申告したとき、特別徴収(給与からの天引き)を選んでしまうと、会社に通知される住民税額が本業よりも増え、経理担当に気づかれてしまいます。
また、SNSやブログでの発信も注意ポイント。思わぬ拡散や検索で、身バレする可能性があります。副業がバレてトラブルになる前に、情報の取り扱いや申告方法には細心の注意を払いましょう。
副業が黙認される職場とアウトになる職場の違いとは?

同じように副業をしていても、「あの人は怒られなかったのに、私だけ指導された…」そんなケース、実際にあるんです。では何が違ったのでしょう?答えはシンプル、「会社の文化とルールの浸透度」が大きく影響しています。
実は、「就業規則に書いてないけど、ウチの部署はやっても平気」という雰囲気の会社も存在します。一方で、ルールに明記がなくても「うちは副業ダメ」という空気のある職場では、ちょっとしたことでも目をつけられがち。
つまり、副業に対する「職場の風土」と「上司のスタンス」が、結果的に自分の立場を左右するのです。
- 業務外の活動に寛容な企業文化がある
- 上司が個人の働き方に理解がある
- 副業の申請制度やガイドラインが整備されている
要約:副業の可否は「会社のルール」よりも「職場の空気」によって左右されるケースが多く、確認と空気読みが肝心です。
「書いてないけどダメ」とされる背景には“昭和的”な価値観も
就業規則に副業のことが書かれていなくても、「副業は悪」という暗黙の価値観が根強い会社もあります。特に長年同じ企業文化の中で育ってきた上司や年配の役職者が多い職場では、その傾向が強いですね。そうした価値観の中では、副業の是非ではなく「会社の顔に泥を塗った」と受け取られることも。ルールだけでなく、職場の人間関係や“空気”も考慮して動くことが、自分を守るうえではとても大切なんです。
就業規則に副業禁止と書いてない場合の「確認ポイント」はここ!
就業規則に「副業禁止」とは書かれていない。でも、だからといって完全に自由に副業していいかというと、そうとは限りません。実は、副業の可否を見極めるには、就業規則の別の項目にヒントがあるんです。
また、書面に載っていなくても、会社独自の社内規定や通達文書で「副業NG」とされていることも。見落としがちなポイントを以下に整理しました。
- 就業規則の服務規律や懲戒規定に該当しないか
- 会社から副業に関する通知・通達が出ていないか
- 人事・総務部門での事前相談が必要かどうか
要約:副業禁止の記載がなくても、就業規則の他項目や社内通知で制限されている可能性があるため、総合的に判断が必要です。
見逃しがちな「副業NG」の記載場所とは?
就業規則の中で、副業そのものに関する項目がない場合でも、例えば「社外活動により業務に支障を与えてはならない」や「企業の信用を損なう行為は禁止する」といった記載があれば、それに副業が該当してしまう可能性があります。また、紙ベースの就業規則とは別に、社内イントラや通達メールなどで副業に関する内規が発表されていることもあるので注意。形式上は“書いてない”けれど、実質的に禁止されているというケースは意外と多いんです。
バレても許される副業・アウトな副業の境界線を整理しよう

実際に、副業をしても何のおとがめもなかった人もいれば、ちょっとしたことで処分を受けた人もいます。この差はいったい何なのか、気になりますよね。ここでは「バレても許されやすい副業」と「バレたらアウトな副業」の違いを、実例ベースで整理してみましょう。
ポイントは、副業の内容・頻度・本業への影響の3つです。たとえ就業規則に副業禁止と書いていなくても、影響が強ければアウト、影響が薄ければ黙認という判断がされるケースが多いのが実情です。
- 不定期で負担が軽い(フリマ・短時間ライターなど)
- 会社と競合しない・利害関係が発生しない
- 本業に全く支障がない範囲で行っている
要約:業務時間外の軽い活動で、会社にとって影響がないものは黙認されやすい傾向にあります。
副業でも“グレー”と“黒”の境界は意外と明確なんです
たとえば、「日曜だけ趣味の教室を開いている」「深夜にフリマアプリをちょこちょこ使ってる」程度なら、本業に影響もないし、周囲の理解も得やすいでしょう。でも、「平日の夜間に居酒屋で週4日勤務」「競合のIT企業で副業ライターとして働いてる」となれば、話は別。本業のパフォーマンスに影響したり、情報漏洩のリスクがあると会社に見なされた時点でアウトになります。内容と頻度を冷静に見極めることが、副業を続けるカギですよ。
副業を続けたいなら「バレない工夫」より「正当な理由」を
副業をしていると、「バレたらどうしよう」とヒヤヒヤする方も多いですが、実は「なぜその副業をしているか」を明確にできるかどうかのほうが大切だったりします。子育ての費用、親の介護、将来の独立準備など、理由がしっかりしていれば、会社側も柔軟に受け止めてくれることがあるんです。
逆に、「副業で大もうけしてやろう」「SNSでインフルエンサーになって本業サボってもいいや」みたいな姿勢が透けて見えると、あっという間に信頼を失ってしまいます。
- 子育て・教育資金など家庭の事情がある
- 将来の独立やスキルアップの準備
- 本業の収入だけでは生活が成り立たない
要約:バレない工夫よりも「なぜ副業するのか」が説得力を持つと、トラブル回避につながりやすくなります。
理由を説明できる副業は、味方も増えやすい
副業がバレたときに「なぜやってるの?」と問われた際、しっかりとした背景や目的があれば、理解者が現れることもあります。「子供の学費のため」「資格取得費用のため」など、人生の目的につながっている副業は、真剣に取り組んでいる証拠にもなりますよね。もちろん、申請が必要な会社なら事前に相談しておくのがベストですが、説明責任を果たせる副業なら、後ろめたさを感じずに継続できるはずです。
誰かの副業が気になるとき、自分はどう振る舞うべき?

職場で「あの人、副業してるらしいよ」と耳にしたこと、ありませんか?あるいは、「明らかに夜の仕事してそう」なんて、つい気になってしまうことも。でも、他人の副業をどう扱うかは、実は自分自身の評価にもつながる大切なポイントです。
密告したい気持ちが芽生えたとき、それが正義感なのか、嫉妬なのか、自分でもわからなくなることもありますよね。でも、「副業してる=悪」ではない今の時代。冷静な対応が求められます。
- 業務に直接支障がなければ基本的に関わらない
- どうしても伝えたい場合は、まず本人に声をかける
- 密告するなら、自分への影響も覚悟しておく
要約:他人の副業に反応する前に、自分の目的や立場を整理し、感情だけで動かないようにするのが大人の対応です。
「チクる人」が周囲から嫌われるのはなぜか
正しいことをしてるはずなのに、なぜか距離を置かれてしまう。「あの人、告げ口する人らしいよ」と陰で言われる…。実はこれ、職場あるあるです。副業の密告に限らず、“他人の行動をジャッジして告げる”という行動は、たとえ正論でも反感を買いやすいんです。もしどうしても気になるなら、まずは信頼できる上司や人事に相談する方が、あなた自身の立場を守ることにもつながります。
「就業規則に書いてないから自由」でも信頼は自分で守る
副業に対するルールが曖昧な職場ほど、最終的には「あなたが信頼されるかどうか」が物を言います。規則に明記されていないからこそ、自分の行動がどう見られているかを意識することが、長く働くうえでとても重要です。
会社のためというより、自分自身の信頼を守るために、誠実に副業と向き合う。たとえ規則に書かれていなくても、そうした姿勢こそがトラブルを回避する一番の近道です。
- 本業を最優先し、副業はサブの立ち位置に
- 副業内容が公に出ても恥ずかしくないかを基準に選ぶ
- 周囲への配慮を忘れず、報連相は丁寧に
要約:就業規則に書いてないからこそ、信頼を損なわない副業のスタイルを意識することが、自分のキャリアを守る鍵になります。
規則より「あなた自身の信用力」が問われる時代に
副業が当たり前になってきた今、求められているのは「副業の中身」よりも「副業とどう向き合うか」という姿勢です。たとえ就業規則に何も書かれていなくても、会社に迷惑をかけず、誠実に働いている姿が伝われば、そこに信頼が生まれます。「自由だから何をしてもいい」という感覚より、「信頼される行動をしよう」という意識を持つことで、トラブルを未然に防ぐことができます。
副業を始める前に確認したい4つのステップ

「副業してみたいけど、就業規則に禁止って書いてないし…どうしたらいい?」そんなときこそ、慎重に段階を踏んで確認することが大切です。曖昧な状態で始めてしまってから後悔するより、始める前のリスクチェックが安心材料になりますよ。
以下の4ステップを押さえておくことで、気持ちよく副業をスタートし、長く続けられる道が開けます。
- 就業規則や社内通知を再確認する
- 本業への影響を冷静に自己分析する
- 副業の内容と業種にリスクがないか調べる
- 必要なら人事・総務に相談しておく
要約:副業の可否は「書いてない=OK」ではないため、始める前にリスクと手順を踏んで確認することで、後悔を避けられます。
「書いてないけど…」から「納得して始めた」に変える安心ステップ
副業を始めたあとに「えっ、それダメだったの!?」と慌てないためにも、始める前のステップがとても大切です。就業規則をチェックしてもわからない場合は、社内イントラや上司にさりげなく確認するのも有効。相談がしにくい場合でも、「この副業、本業に影響しないかな?」「業務時間外でも誤解を招かないかな?」と、自問しておくだけで判断基準が明確になります。
就業規則に副業禁止と書いてない職場でも、うまく副業を続けるコツ

副業を始めるなら、できるだけ長く続けたいですよね。就業規則に副業禁止と明記されていなくても、立ち回り方を間違えると、思わぬ反発やトラブルを招くこともあります。長く穏やかに副業を続けるためのコツ、ここでまとめておきます。
特別な才能やスキルよりも、ちょっとした気配りや周囲への配慮こそが、副業継続の秘訣になるんです。
- 本業のパフォーマンスを落とさないことを最優先
- 副業先やSNSで会社名・本業情報を出さない
- 誰かに話すときは信頼できる人にとどめる
要約:副業を続けるカギは「目立たず、迷惑をかけず、きちんとこなす」その姿勢にあります。
「副業は悪」じゃないけど、「副業の仕方」は見られている
今や副業はめずらしいことではなくなりました。でも一方で、「どうやって副業してるか」は、周囲から意外と見られています。「あの人、しっかり本業もこなしながら副業もやってるよね」と思われればプラス評価。でも逆に「副業のせいでミス増えてない?」と思われたら、本末転倒です。副業の中身以上に、「やり方」で評価される。そこを意識して行動すれば、自然と良い結果に結びついていきますよ。
就業規則に副業禁止と書いてないときこそ、慎重な判断を

ここまで読んでくださってありがとうございます。就業規則に「副業禁止」と明記されていないとき、「じゃあ自由にやってOKなんだ!」と思いたくなりますよね。でも、実際にはそれほど単純じゃないのが現実。
副業が会社にバレる原因は思いがけないところにあり、その後の対応や処分も会社次第。書いてないからこそ、「何を見て、誰に聞いて、どう判断するか」がとても大事になってきます。
本業とのバランス、職場の空気、自分の信頼…これらを守りながら副業をするには、以下のポイントを意識しておくと安心です。
- 就業規則だけでなく“空気”や“慣例”も確認する
- 本業のパフォーマンスを落とさないことが信頼を守るカギ
- 何かあったときに説明できる「正当な理由」を持つ
要約:「就業規則に書いてない=自由」ではないからこそ、自分を守るための判断基準と行動が必要です。
未来の自分を守るために、今日からできること
副業は人生を豊かにする手段のひとつ。でも、本業の信頼を損ねてしまっては元も子もありません。就業規則に副業禁止の記載がなくても、何が自分にとって最善なのかを考えたうえでの判断が、結果的に一番後悔のない選択になります。
「やっていいか」だけでなく「どうやるか」「誰と共有するか」「どんな姿勢で取り組むか」までを意識して、安心して続けられる副業スタイルを目指してみてくださいね。あなたの働き方が、もっと自由でしなやかになりますように。

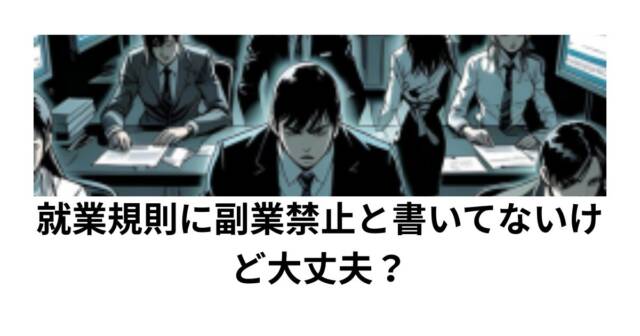









コメント