「専任の宅建士だけど、副業してもバレないかな…?」そんな不安、ありませんか?副業解禁の流れが進む中、不動産業界ではまだまだ慎重にならざるを得ない事情があります。特に専任の宅建士として登録している方は、“バレたらどうなるの?”と不安を抱えながらも、実際のルールやリスクをきちんと知らない方も多い印象です。
この記事では、宅建業法や実際の相談事例をもとに「副業がバレる条件」「法律上OKなケース」「バレないための対策」など、気になる情報をわかりやすく丁寧に解説していきます。
専任の宅建士は副業できない?常勤性・専従性の意味をわかりやすく解説

副業しても問題ないと言われる世の中ですが、宅建業界はちょっと特殊。特に「専任の宅建士」に課せられる義務は、他業界の副業ルールとは違う独特のルールがあるんです。ここでは、まず「常勤性」「専従性」ってなに?というところから、一緒に見ていきましょう。
宅建業法で定める「専任性」とは何か?副業との関係性
宅建業法では、営業所ごとに「専任の宅地建物取引士」を設置することが義務付けられています。しかもその“専任”というのは、ただ資格を持っていればいいという話ではなく、「営業時間中は常にその事務所で勤務していること」「他に専念すべき仕事を持っていないこと」が求められます。
つまり、他の会社に所属しているとか、平日昼間に別の仕事をしているというのはNG。ただし、夜間や休日、そして一時的な単発バイトが「専任性を欠く」とまでは判断されないケースもあるのです。
副業がバレる原因とは?勤務時間と労働契約の落とし穴
「宅建業法的にOKかどうか」以前に、副業がバレる原因は意外と身近なところに潜んでいます。例えば勤務先に提出している就業規則や、給与明細、SNSでの副業発信など。副業しているつもりがなくても、情報がどこからか漏れてしまうことがあるんですね。
- 年末調整や住民税から給与の二重計上が見つかる
- SNSや知人経由で社内に情報が回る
- 勤務時間との重複で発覚する
このように、税務署や役所よりも先に「社内バレ」の可能性の方が圧倒的に高いんです。
勤務先が副業に寛容でも油断は禁物
最近では「副業OK」と掲げる不動産会社も増えてきました。ただし、「法律に抵触しない範囲で」という注釈がついているケースも。これはつまり、宅建業法などの規制を破らない範囲であればOKという意味で、完全自由というわけではないんですね。
単発バイトならOK?ラベル貼りやサンプリング配りは合法?
「土日にイベントで1日だけラベル貼りの仕事をしたい」「配布スタッフとして短時間働きたい」と思うことってありますよね。実はこのような内容は、宅建業法に明確に抵触しないケースが多いんです。ポイントは「不動産業務に直接関係しない」こと。
つまり、宅建士としての立場や資格が関わってくる内容でなければ、宅建業法的にはOKと判断される可能性が高いんです。ただし、注意したいのは、単発とはいえ“勤務実績”として記録に残るような働き方をしてしまうと、常勤性に疑義が生じることもある点です。
「ラベル貼り程度だから大丈夫でしょ」と油断して始めると、思わぬところで足元をすくわれるかもしれません。
副業内容が“非不動産業務”でも注意は必要
たとえば、チラシ配りや棚卸し作業など、全く異業種の仕事であっても「継続性がある」「労働契約を結んでいる」「副業先が登録されている」などの要素があると、“専任性の喪失”とみなされるリスクがあるんです。
不安なときは、登録している都道府県の「不動産業課」に確認をとるのが安心。電話一本で教えてくれることもありますし、記録に残したければ文書での回答依頼もできますよ。
常勤性・専従性を損なうケースとは?宅建業法でNGな副業例
宅建士として勤務するうえで守らなければならないのが「常勤性」と「専従性」。この2つの要件を満たしていないと、専任の宅建士として登録できません。そして、副業の内容によっては、このどちらか、あるいは両方を損なってしまう恐れがあります。
- 平日昼間に他社で社員として勤務している
- 別法人の役員や代表として活動している
- 不動産業に関係する副業を他社で行っている
こうした副業は、どれも「専任性がある」とは判断されにくい内容です。
NG副業の判断基準は“誰が見ても常勤じゃない”と思われるかどうか
「専任性」は厳密な数値で決まるものではなく、総合的な判断です。たとえば「日中に他社で勤務実績がある」「週に数日別の会社の役員業務をしている」などの記録が残れば、常勤性を欠くとされる可能性がぐっと高まります。
逆に言えば、休日や業務時間外にちょこっとだけ活動している内容で、宅建士としての勤務に支障が出ていない場合は、許容されるケースも多いということ。ただし、最終的な判断はあくまで行政の裁量です。グレーな範囲の副業は控えるのが無難です。
副業がバレるリスクを回避するには?専任宅建士が知っておくべき対策
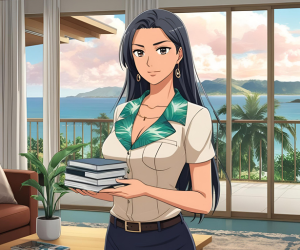
副業そのものが悪いわけじゃない。でも、専任の宅建士という立場上、うっかり「バレた…」となると、信用も職も失いかねないリスクがあるんです。そうならないために、事前にしっかり対策しておくことが大切ですよね。ここでは、現場で実際にトラブルを回避している方の工夫を交えながら、安心して副業を続けるためのポイントをご紹介します。
勤務先の就業規則と労働契約を事前に確認しよう
一番最初にやるべきことは、会社に提出している「就業規則」と「雇用契約書」を見直すこと。中には「副業禁止」と明記されていたり、「宅建業法に反しない限り可」となっていたり、曖昧なケースもあります。ここを確認せずに勝手に副業を始めると、後でトラブルになる可能性があるんです。
特に注意したいのが、「副業報告義務がある」と書かれている場合。届出をしていなかったことがバレた途端、就業規則違反になってしまうこともあります。まずは「自分の働いている会社が副業をどう捉えているか」をしっかり確認することが、最初の一歩です。
宅建業者への届け出不要でも安心できない理由
「行政に届け出てないからセーフでしょ?」と思いがちですが、実はこれも落とし穴。宅建業法では、専任の宅建士の氏名・勤務先・勤務形態などを変更した場合、届け出が必要です。副業そのものに対しては届け出義務がないとはいえ、勤務時間や常勤性に影響するような働き方をしていると、結果的に届け出内容と実態が異なることになり、問題視されることがあります。
- 副業により本業の勤務時間が変更された
- 他社で勤務実態があると判断された
- 行政指導を受ける可能性がある場合
副業の内容だけでなく、その働き方が「専任性」にどう影響しているかが重要なポイントになります。
自分を守るために“グレーゾーン”は避けるのがベスト
宅建士としてのキャリアを守るためには、「バレなきゃ大丈夫」ではなく、「バレても堂々と説明できる」状況にしておくのが理想。できれば副業の内容・頻度・時間帯などは、すべて記録に残しておくと安心です。トラブルが起きたとき、自分の正当性を証明できる材料になりますよ。
もし「これってグレーかな?」と迷う場合は、登録している都道府県の不動産業課に確認をとることをおすすめします。意外と親身になって答えてくれるので、心配事があれば抱え込まずに相談してみましょう。
専任宅建士が副業してもOKなパターンと実際の体験談

では、実際に副業をしている専任の宅建士さんは、どんな働き方をしているのでしょうか?ルールを守りながら、上手に収入をプラスしている人たちの実例を見てみると、「あ、これなら私にもできそう」と思える工夫がたくさんあるんです。
実際に副業している宅建士の声|「単発アルバイトOKだった」体験談
ある宅建士の方は、土日に知人のイベントで単発のアルバイトを時々しているそう。内容は商品の搬入手伝いや、受付業務。いずれも不動産業とはまったく関係のない仕事で、勤務先にも事前に伝えたうえで行っているとのこと。
もちろん「宅建士」としての仕事に影響が出ないように、勤務時間帯や体調にも配慮していて、これまで一度も問題になったことはないそうです。
小さく始めて報連相をしっかりすれば副業も可能
ポイントは、「正直に申告しておくこと」「働く時間帯を調整すること」「宅建業務に支障が出ないよう配慮すること」。この3つを守っていれば、会社側も柔軟に対応してくれるケースが増えてきています。
働き方が多様化する今、副業の価値も見直されています。常識的な範囲内で、誠実に対応すれば問題が起きにくいという声は多く、前向きに検討してもよい選択肢かもしれません。
県の不動産業課に問い合わせた結果|回答は「個別判断」だった
実際に、都道府県の不動産業課に電話で問い合わせたという方からは、「基本的に業法に抵触しない限りは、勤務時間外であれば問題ない」との回答を得たという話もあります。
ただし、「最終的には状況を見て個別に判断します」との但し書きもあったとのこと。行政側も一律には判断できないグレーゾーンがあるため、「状況を説明できるようにしておく」ことが求められているんですね。
- 勤務先の名称と登録番号を手元に準備する
- 副業の内容・頻度・時間を具体的に伝える
- 文書での回答を希望する場合はその旨も伝える
相談は恥じゃない!むしろリスク管理の一環として活用しよう
「わざわざ役所に聞くなんて…」と思う方もいるかもしれません。でも、問い合わせることで万一のトラブルを避けられるなら、その時間と手間は大きな価値があります。
自分のキャリアを守るためにも、「聞いてみる」「記録に残す」「堂々と働く」この姿勢が、副業時代の新しいスタンダードになってきていると感じます。
SNSや掲示板に見るリアルな副業事情と意外な盲点
「専任の宅建士って副業しちゃダメなの?」「休日に単発で働いたらまずいのかな?」こういった声、SNSや掲示板でもよく見かけます。なかには「バレて大変だった」「堂々とやってるけど今のところ問題なし」といった体験談も多く、さまざまなケースが飛び交っています。
注目すべきは、実際にバレたケースの原因。SNSで副業の様子を投稿していたり、副業先の求人情報で氏名が確認できてしまったなど、「思わぬところから情報が漏れている」パターンが多いんです。
副業内容よりも“情報の扱い方”が命取りに
特にSNSやブログをやっている方は要注意。投稿の中で自分の仕事や活動内容が特定できてしまうと、たとえ悪気がなくても「副業してるのでは?」と疑われてしまう可能性が出てきます。
リアルの人づきあいでも、「副業してるってあの人言ってたよ」と噂が広まることもあるので、必要以上に発信しない・話さないというのもリスク管理のひとつですね。
他の専任資格者との違いは?公務員や士業との比較で見える本質
副業といえば、公務員の副業解禁の話題もよく取り上げられていますよね。でも、専任の宅建士は公務員と違って「法律で副業禁止」と明記されているわけではありません。その代わり、「常勤性」や「専従性」といった考え方があるため、実質的には制限される部分があるという特徴があるんです。
- 公務員:法律で明確に副業が制限されている
- 社労士・税理士:開業していれば副業は自由だが届出が必要
- 宅建士(専任):専従・常勤性を満たす必要があるため実質制限あり
資格ごとに違う“副業の自由度”を知ることがリスク回避の第一歩
自分の資格がどんな位置づけなのかを知っておくと、他の業界と比べてなぜ注意が必要なのかが見えてきます。宅建士という国家資格は、その専門性と責任の重さゆえに「専任であること」が重視されるため、兼業との両立が難しくなるんですね。
それでも、工夫次第で安全に副業を続けることは可能。大切なのは、“一人の判断”で突っ走らず、法的根拠と勤務先の理解を得ながら進めていく姿勢です。
【結論】副業はできる?専任の宅建士が安心して働くための判断ポイント

ここまでの内容をまとめると、専任の宅建士でも副業は「条件付きで可能」といえます。ただし、それはあくまで“業法を守ったうえで、勤務に支障がない範囲で”という条件がそろった場合に限られます。
むしろ、勝手な判断で始めてしまった副業がバレてしまうと、宅建士資格だけでなく職も失いかねない…それだけは避けたいですよね。だからこそ、「内容・時間・契約形態」を整理し、「行政や会社に説明できる」状態をキープしておくことが大切です。
- 副業内容が不動産業と無関係である
- 勤務時間外・休日にのみ行っている
- 会社・行政に報告できる状態にしている
「バレない」より「バレても困らない」副業を目指そう
副業のリスクは、「していること」そのものよりも、「隠していること」によって大きくなります。正直に、透明性をもって対応することが、結局は一番自分を守ることにつながります。
宅建士としての誇りを持ちながら、無理のない範囲で副業をする。その選択が、これからの時代を生き抜く力になるかもしれません。
よくある質問(FAQ)|専任宅建士の副業に関する素朴な疑問
Q. 休日にイベントスタッフのバイトをするのは大丈夫?
A. 基本的には問題ありません。ただし、常勤性を損なうほど頻度が高くなる場合は注意が必要です。不動産業と無関係な内容で、勤務時間外・休日に行う一日限りの単発バイトであれば、宅建業法に直接違反するものではないと考えられています。
Q. 副業がバレたら、宅建士登録を抹消されることはありますか?
A. バレた内容が「常勤性・専従性を満たしていない」と判断された場合、登録の抹消や指導の対象になる可能性があります。ただし、すべての副業が一律でNGというわけではなく、「どのような勤務状況か」が大きく関わってきます。
Q. 他の宅建業者で一時的に働くことは副業扱いになりますか?
A. はい、完全にNGです。他の不動産業者で働くことは、単発であっても「専任性の喪失」とみなされるため、最も避けるべき行為の一つです。絶対にやめておきましょう。
Q. 名義貸しや無報酬の活動も副業に該当しますか?
A. 名義貸しは違法ですし、たとえ無報酬でも業務に携わったとみなされる場合は副業と判断されることがあります。お金の有無よりも、「業務実態があるかどうか」が重要ですのでご注意ください。
Q. 副業を始めたいとき、最初にやるべきことは?
A. 就業規則・労働契約書の確認、不動産業課への相談、そして副業内容の整理です。特に記録を残しておくことは、あとあと自分を守る材料にもなります。できれば副業内容を明文化して会社へ報告しておくのがベストです。
副業を考える際には、法律・実務・働き方のバランスを見ながら、焦らず少しずつ情報を整理していくことが大切です。無理のない働き方で、安心してキャリアを続けていきましょうね。
最後までお読みいただきありがとうございました!





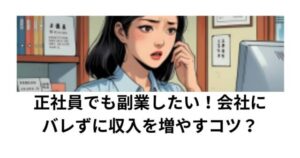
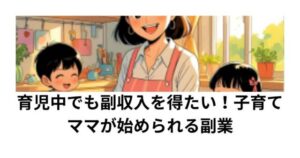

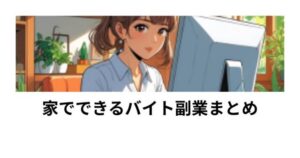


コメント